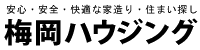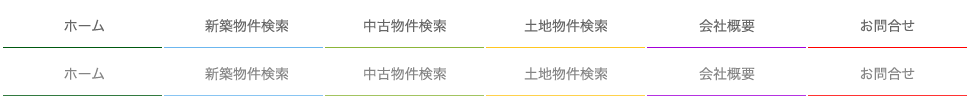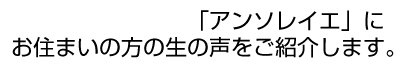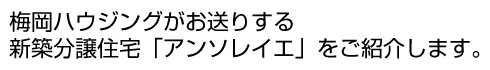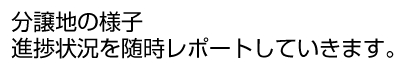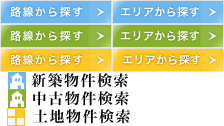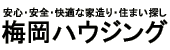梅岡ハウジングの新築分譲住宅 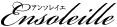
 NEW
NEW
アンソレイエ辻町
家族のつながりを感じながら心安らぐ住まい
モデルハウスが完成しました
生駒駅・東生駒駅 2駅利用可能
幼稚園・小学校 徒歩8分で通学も安心
アンソレイエ鳥見町
気品ある街並みと閑静な住環境に包まれて
駅徒歩12分、良好な住環境
ゆとりの敷地65坪、限定2区画分譲
南向き、日当たり良好
アンソレイエ俵口町
家族の夢がいっぱい詰まった家
駅徒歩14分、利便性高い俵口町
第3期2区画分譲
生駒山を望む眺望に優れた分譲地
アンソレイエ北新町Ⅱ
広がる空と緑を楽しむ潤いあるロケーション
分譲地内にモデルハウスあり
暮らし充実、駅近スローライフを実現
高台の緑豊かなロケーションで眺望良好
あなたのライフスタイルに合わせたあなただけの空間。
梅岡ハウジングがお送りする新築分譲住宅「Ensoleille(アンソレイエ)」は、間取りを自由設計出来ます。